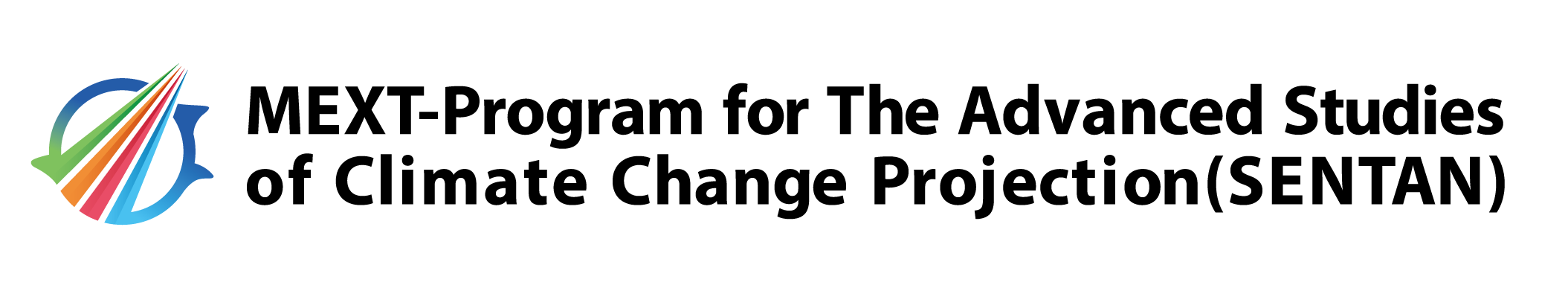 |
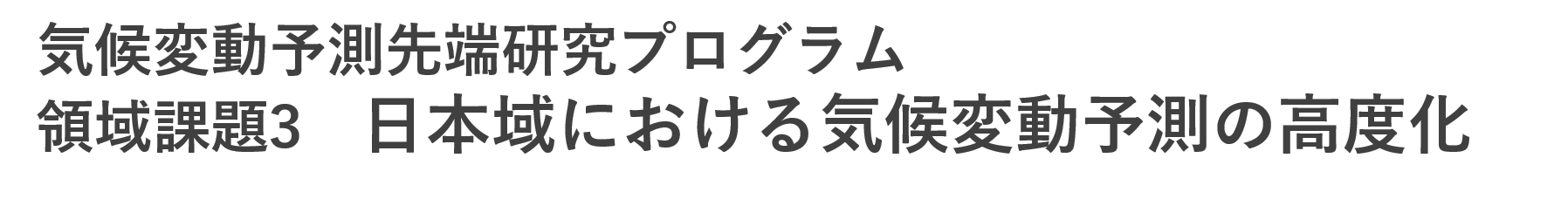 |
気象業務支援センター |
令和6年度の業務目的
2020年以降の温室効果ガス排出削減のための国際的枠組みであるパリ協定が2016年12月に発効しました。
この中では、産業革命後の温度上昇目標として2.0℃、また努力目標として1.5℃が掲げられています。
パリ協定では、5年ごとに参加各国の温暖化対策の実施状況等の報告の義務があります。
これに伴い国内でも5年サイクルでの温暖化関連各種レポート(日本の気候変動2020、影響評価報告書2020等)、あるいは我が国のナショナルシナリオ(気候予測データセット2022)が発行されています。
また、パリ協定の実現に向けて我が国政府も、カーボンニュートラル2050(CN2050)を宣言しています。
政府による、ナショナルシナリオに含まれる気候予測データセットの気候変動適応策への活用はすでに始まっています。
本領域課題は、今後一層必要性が増してくる国・地方自治体による気候変動適応策の検討.実施や民間企業の気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)における気候変動に伴い増加が懸念される異常気象等の物理リスク評価などにともなうユーザーニーズに対応することを目指します。
その為に、温暖化対策検討の根拠となる我が国のより高精度なナショナルシナリオの提供を目指し、高精度のモデルのアセンブル、2021年8月に承認された気候変動に関する政府間パネル第1作業部会(IPCC/ WG1)の第6次評価報告書の評価で使われたSSP(共通社会経済経路)シナリオによる計算実施から気候変動に伴う気候ハザードの要因分析、温暖化予測データの効果的な配信に向けた研究を行なうことを目的とします。
本課題では、以下のサブ課題及びワークスで研究に取り組みます。
サブ課題(i)「日本域の気候変動の予測システム開発とメカニズム解明」では、気象業務支援センター(JMBSC)が海洋研究開発機構(JAMSTEC)とともに、領域気候モデル、海洋モデルを含む高精度モデルの開発とアセンブルを行ない、さらにSSP(共通社会経済経路)シナリオによる計算実施から気候変動に伴う大規模な気候ハザードの要因分析を実施します。
サブ課題(ii)「地域・流域の適応策推進に向けた気候変動予測情報の創出・極端現象メカニズムの解明」では、北海道大学が、東北大学、名古屋大学、JAMSTEC、JMBSCとともに、ユーザフレンドリーな情報の創出を目指して、メガアンサンブルデータの改良と実行、イベントアトリビューション研究の推進、AI等を活用した低頻度極端現象の抽出方法等の研究開発を専門家の参加を得て行ないます。
サブ課題(iii)「海外の脆弱地域における高精度気候予測データセットの創出」は、JMBSCが中心となり、海外関連研究機関と連携を取りつつサブ課題(i)、(ii)の成果を世界の脆弱地域に還元する研究を実施します。
サブ課題横断で実施するワークス「プロダクツ利活用促進」は、JMBSCとJAMSTEC中心で、温暖化予測データをユーザーに効果的に提供するシステムをデータ統合・解析システム(DIAS)上に構築・運用し、データの利活用を促進します。
このワークスは本領域課題参画者と本領域課題内外のユーザーを繋ぐ役割を担い、本領域課題のテーマである「行動につながる気候科学」の円滑な実現を目的とします。

令和6年度の業務方法
サブ課題(i):日本域の気候変動の予測システム開発とメカニズム解明
大気モデル解像度60kmの全球気候変動予測システム Time Sequential Experiments with Coupled model(TSE-C)について、 代表的な温暖化シナリオに基づく20世紀中頃から21世紀末まで連続した温暖化予測アンサンブル実験を行う。 その結果について、過去再現期間の気候再現性能の検証、および現在から将来にかけての連続的気候変化の初期解析を行う。 また、大気モデル解像度20kmのTSE-Cについて、気候再現性の解像度依存性を低減させるシステム改良を引き続き行い、 20世紀後半から21世紀前半までの過去再現実験および代表的な温暖化レベルでの将来気候実験を開始する。

(i)-aで実施される大気モデル解像度60kmTSE-Cによる温暖化予測アンサンブル実験を元に、20km格子の地域気候モデル(NHRCM20)を用いて力学的ダウンスケーリングを実施する。 さらにそれを5km格子の地域気候モデル(NHRCM05)を用いてダウンスケーリングし、再現性や既存の類似のデータとの違いを確認する。 過去再現実験の検証や将来予測実験の妥当性検討のため、NHRCM05等の領域モデルを用いて、最新の日本の長期再解析データ(JRA-3Q)を5km格子までダウンスケーリングする。 このデータを既存の長期再解析データJRA-55からのダウンスケーリングデータと比較して妥当性を検証した上で、TSE-Cからのダウンスケーリング結果の検証に使用する。 令和4年度に開発した領域気候モデル(asuca領域気候版)に移植した都市モデルSPUC、及び陸面モデルeSiBに移植したSMAPのアルベドコンポーネントの動作確認、再現性を検証する。

令和5年度に作成した初期値および(i)‐aで実施される温暖化予測アンサンブル実験により作られた海洋駆動外力を用いて、 現在気候および代表的な温暖化シナリオに基づく海洋ダウンスケーリングプロダクトの作成を継続する。 気候予測データセット2022(DS2022)日本域海洋予測データに対して行った解析と同様の方法で、このプロダクトに対する初期解析を行う。 日本近海の高解像度海洋再解析データに関して、1960年から2020年までのメインプロダクトの作成を完了し、結果の検証を行う。

TSE‐Cによる時間連続実験について、過去・現在気候に関する再現性能を評価する。 TSE‐Cによる全球実験およびそれを境界値とした日本域大気‐陸面モデル実験に基づいて、日本付近の極端気象および大規模大気場の過去から将来の時間連続的な気候変動に関する初期解析を行う。 また、旧全球気候予測システム(MRI‐AGCM3.2)による全球実験およびそれを境界値とした日本域実験の解析を引き続き行い、CMIP6全球実験の解析を併用しメカニズム理解および不確実性定量化のための検討を行う。


サブ課題(ii):地域・流域の適応策推進に向けた気候変動予測情報の創出・極端現象メカニズムの解明
日本全国を網羅する高解像度の気候再現・予測データ(改良版d4PDF)を近年に延長した計算を行う。 既往顕著事例および各気候変動予測実験における最悪クラスの台風事例について令和5年度に高度化した最新の非静力学モデルCReSSによる力学的ダウンスケーリング(DDS)を進め、 その結果を分析する。また、シームレス実験とタイムスライス実験の長所を最大限に活用可能な数理手法の開発を推進し、過去から将来に亘る時間連続したアンサンブル気候データを作成する。 加えて、AI等の多岐に亘る数理手法を活用し、単一モデルの有する不確実性評価に向け、 d4PDFのDDSデータからマルチモデルのDDSデータを近似し、マルチモデルでのDDS結果に相当するデータの作成を行う。 当該手法群から創出された、任意の空間・時間スケールに対応した高度なアンサンブル気候情報及び既存実験プロダクトを用い、低頻度極端現象の生起要因別の分析等を実施する。 これにより、地域・流域が有するリスクの将来変化の解明に資する気候情報の創出を推進するとともに、その知見をサブ課題(ii)‐b、(ii)‐c及び領域課題4に共有する。

d4PDF過去・非温暖化延長実験とそれを元に5kmメッシュ以下にダウンスケーリングしたデータを用いて、 これまで評価できていない近年の極端事象に対して温暖化の影響を評価するとともに、令和6年度に極端気象が発生した場合はその現象も評価対象とする。 アクショナブルEA研究に向けて、領域課題1・4と連携して機動的EAの開発を進め、極端気象が発生した場合は速やかに温暖化影響を評価できるような体制を構築する。 気温についてはほぼ完成したため、過去の猛暑を対象とした評価を進めながら、令和6年度に猛暑が発生した場合は速やかに機動的EA手法を用いて猛暑に対する地球温暖化の寄与を評価する。 降水については、領域課題4が中心となって、極端降水に対する地球温暖化の影響を極値統計解析により評価する手法を開発する予定であるが、その開発に必要なデータを共有する。 極端気象事例が発生した時の天気図に着目し、類似の天気図の場合の地球温暖化に伴う平均的な気候変化(総観場分類に基づく気候差分)を求め、 それを用いて主に北海道の極端気象事例を対象とした擬似温暖化あるいは擬似非温暖化実験を試行する。 これまでに実施した東アジアにおける複数年の感度実験結果や気候予測データセット2022を用い、日本の猛暑に影響を与えるアジアスケールの遠隔作用等について解析する。

観測データ、気候予測データセット2022、改良版d4PDF及び(ii)-aで創出される時間連続したアンサンブル気候情報への分析を通して、 災害に直結する各種極端現象のティッピング・ポイントとなる外力や最大規模の外力を推定する。 本領域課題による多岐にわたる実験プロダクトへの分析結果を領域課題4やサブ課題(iii)ならびに関連する研究コミュニティ等と共有する。 また、これらの関係機関との連携を通して、時間軸を踏まえた適応策の展開において、考慮すべき極端現象の外力規模およびその気候・気象学的な発生要因・メカニズム、温暖化応答を分析する。 加えて、対象とする気候データセットの差異(解像度、側方・底面境界条件、バラメタリゼーション、温暖化レベル)が気候外力に及ぼす影響の定量化及びその気候・気象学的要因の評価を進める。


サブ課題(iii):海外の脆弱地域における高精度気候予測データセットの創出
新たな非静力学地域気候モデルを海外領域に適用するための各種調整作業を行う。 気候変動に対し脆弱な地域から研究者を招聘し、当該地域の気候予測データを創出する。 日本の気候に大きな影響を与えると考えられるアジアモンスーン地域の詳細な気候を調べるため、地域気候モデルを用いた数値実験を行い、降水現象に着目して解析する。 さらに、協同地域ダウンスケーリング実験-東アジア(CORDEX-EA)の領域を対象にした地域気候モデルによるテスト実験を行い、モデルによるシミュレーション結果の再現性を調べる。

領域課題全体での取り組み
1) 公開サイトの充実:「気候予測データセット2022」の公開サイトについて、データ利用者に対する問い合わせ回答や問い合わせを踏まえたコンテンツの拡充を実施する。
2) DIASとの連携:また、DIASと連携してデータ利用のための環境整備についての検討を引き続き行い、ツールの設計・試作を推進する。
3) ワークショップの開催:気候予測データの開発者と利用者の相互理解を深めるために、相互のコミュニケーションを促進する場をつくる。 そのために課題3・4で連携してデータ利活用に関するワークショップや研究会などを実施する。 また、DIASの主催するハンズオンワークショップ等に協力する。国際会議(GEWEX一OSC)で気候変動予測先端研究プログラムの成果を国際的に打ち出す。 公開型の気候変動・ハザード予測の研究会を開催すると共に、領域課題3・4連携会合を開催し、相互の進捗を共有すると共に、領域課題間連携の実施計画について議論する。

design by tempnate